新規事業立ち上げにおけるコアメンバーの重要性
新規事業の成功には、優れたアイデアや資金調達だけでなく、その基盤を支える「コアメンバー」の存在が不可欠です。特に日本企業においては、信頼関係やチームワークを重視する文化が根付いているため、誰をコアメンバーとして選定するかが事業の成否を大きく左右します。
コアメンバーは単なる実務担当者ではなく、会社のビジョンや価値観を共有しながら、新しい課題に柔軟に対応できる人材であることが求められます。日本企業では、「和」を大切にしつつも、現状維持バイアスを乗り越えて変革をリードできる人材を見極めることがポイントです。
また、新規事業では既存事業とは異なるスピード感や不確実性への対応力も重要となります。したがって、経歴やスキルだけでなく、未知の領域にも前向きに挑戦し続けられる姿勢や、周囲を巻き込むコミュニケーション力も重視しましょう。
コアメンバーの採用と選定は、一度失敗すると組織全体の士気や方向性にも影響を及ぼします。だからこそ、「誰と一緒に始めるか」を慎重に考え抜くことが、日本的な組織運営においても新規事業成功のカギとなります。
2. 採用活動の現実と課題
新規事業立ち上げ期におけるコアメンバーの採用は、理想と現実のギャップに直面する場面が多々あります。特に日本国内においては、採用市場の流動性が低く、「即戦力人材」を求める企業が集中しているため、優秀な人材を獲得する難易度が年々高まっています。
日本の採用市場における独自の課題
日本では新卒一括採用が依然として主流であり、中途やベンチャー企業への転職には慎重な姿勢を持つ求職者が多いです。そのため、新規事業やスタートアップで「初期メンバーになりたい」と考える人材はごくわずかという現状があります。さらに、大手志向・安定志向が根強く、挑戦的な環境を選ぶことへの心理的ハードルも高いです。
採用活動でよくある落とし穴
| 落とし穴 | 具体例 |
|---|---|
| ミスマッチ採用 | カルチャーやビジョンへの共感よりスキル重視で採用した結果、早期退職につながるケース |
| 過度な期待値設定 | 「何でもできるオールラウンダー」を求めすぎて、現実的に該当する人材が集まらない |
| リファラル頼みすぎ問題 | 知人・友人経由でしか採用せず、多様性や客観性を欠いた組織になる |
リアルな体験から学ぶ教訓
私自身も過去に「この人なら大丈夫だろう」と思って入社してもらったものの、事業スピードや役割変化について来れず、結局短期間で離脱されてしまった苦い経験があります。新規事業だからこそ、「やってみないと分からない」部分は多いですが、最初から全てを背負える人材などほぼ存在しません。
正直なところ、日本の採用市場では「完璧なコアメンバー候補」を探すよりも、ポテンシャルや価値観を重視し、ともに成長できる素地があるかどうかにフォーカスすることが重要です。
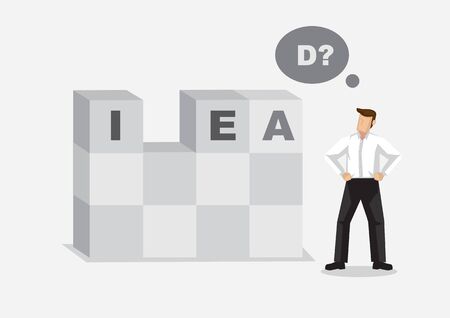
3. 求める人物像の明確化と伝え方
新規事業の立ち上げ期において、どんな人材をコアメンバーとして迎えるかは、その後の組織や事業成長に大きな影響を与えます。ここでまず重要なのは、求める人物像を「言語化」することです。つまり、理想とするスキルや経験だけでなく、価値観や行動特性まで具体的に落とし込み、曖昧さを残さないことが肝心です。
なぜ人物像の明確化が必要なのか
立ち上げ期はリソースも限られ、一人ひとりの役割が非常に重くなります。そのため「何でもできる人」「柔軟性がある人」といった抽象的な表現ではなく、「自分ごととして考え抜き、泥臭く行動できる人」「前例のない課題にも前向きにチャレンジする姿勢」など、実際に現場で必要となる資質を明確にしましょう。
日本人ならではの共感ポイントへの配慮
日本では「チームワーク」や「誠実さ」「謙虚さ」といった価値観が重視される傾向があります。採用メッセージや求人票でも、「個の力を発揮しながらもチーム全体の成果に貢献できる方」「一緒に汗をかきながら成長していける仲間」といった表現は多くの候補者に響きます。
社内外への伝え方の工夫
候補者には会社説明会やカジュアル面談で代表自らが直接思いを語ったり、既存メンバーとの座談会を設けてリアルな雰囲気を感じてもらうことも効果的です。また社内には、新規事業でどんな価値観・姿勢が求められるのかを定期的に共有し、現場でぶれない判断基準とすることも忘れてはいけません。
「この会社で、このフェーズだからこそ必要な人材とは何か?」を言語化し、納得感ある形で伝えること。それが強い組織づくりへの第一歩になります。
4. カルチャーフィットと価値観のすり合わせ
新規事業立ち上げ期においては、個々のスキルや実績以上に「組織文化」とのフィット感がコアメンバー採用の成否を大きく左右します。特に日本の職場文化では、チームワークや和を重んじる雰囲気、暗黙の了解や配慮などが日常的に求められます。いくら優秀な人材でも、このカルチャーに馴染めないと、組織としての推進力が落ちてしまうことも少なくありません。
日本企業に多い価値観とは
| 価値観・行動様式 | 具体例 |
|---|---|
| 和を重んじる(協調性) | 会議で意見が割れた際にも、多数派に配慮しつつ発言する |
| 空気を読む(忖度) | 相手の発言意図や表情から本音を汲み取る |
| 長期的な関係構築志向 | 短期成果よりも信頼構築を優先する行動 |
| 役割分担への柔軟性 | 状況に応じて自分の担当以外にもフォローする |
| 上下関係・年功序列への配慮 | 目上の人への敬意を忘れないコミュニケーション |
カルチャーフィット確認のための実践的なすり合わせ方法
- 面接時の対話型質問: 形式的な質問だけでなく、「実際に過去どんなチームでどんな役割を果たしたか」「納得できない指示があった時どうしたか」など、日本独特のチームワーク環境下での対応力を掘り下げる質問を行います。
- 現場体験・ジョブシャドウイング: 入社前に現場見学や1日体験入社を通して、既存メンバーとの相互理解の機会を設けます。お互いの違和感ポイントを率直に話し合える場作りが重要です。
- バリュー共有ワークショップ: 自社独自の価値観や行動指針についてグループディスカッションを実施し、候補者自身がどう感じ、どこまで共感できるかをチェックします。
- フィードバック文化づくり: 新メンバーにも既存メンバーにも、お互いへのフィードバックを定期的に行う習慣を促すことで、価値観ギャップを早期発見&解消します。
失敗例から学ぶ:カルチャーミスマッチが招くリスク
一部の新規事業立ち上げ現場では、スキル重視で採用した結果、「空気が読めず孤立する」「周囲との摩擦で生産性が落ちる」「本人が早期退職してしまう」といったケースも多く報告されています。だからこそ、コアメンバー選定段階から「この人と一緒に長く働けるか?」「自社ならではの価値観とズレはないか?」という視点で慎重なすり合わせプロセスが欠かせません。
まとめ:カルチャーフィットは事業成功への土台
新規事業フェーズではスピード感や個々の能力だけでなく、「同じ方向を向いて走れる仲間」であることが最重要条件です。カルチャーフィットと価値観共有は単なる採用活動ではなく、組織づくりそのもの。焦らず丁寧なすり合わせを心掛けましょう。
5. 立ち上げ期ならではの組織設計のコツ
柔軟性を重視した組織デザインの重要性
新規事業やスタートアップの立ち上げ期においては、従来型のピラミッド組織よりも、フラットで柔軟な組織設計が圧倒的に機能します。例えば「役割は流動的」「肩書きにこだわらない」「必要に応じて意思決定プロセスを変える」などが実際には効果的でした。私自身も、初期メンバー全員が営業・開発・マーケティングなど複数領域を兼任し、日々タスクを見直すことで無駄な会議や手続きが削減できた経験があります。
コミュニケーションのハードルを下げる工夫
立ち上げ期は「情報共有」によるロスや齟齬が命取りになりかねません。そのため、週次の全体朝会や日報Slack投稿など、小まめな情報共有ルールを明確化することが肝要です。一方で、あまりにも管理を強化しすぎると現場の自律性が損なわれます。私の失敗談としては、「進捗報告フォーマット」を細かく作りすぎた結果、現場メンバーが本音を話さなくなり、逆にトラブルの早期発見が遅れたことがありました。「最低限で最大効率」のバランス感覚は常に意識しましょう。
「ベストプラクティス」は疑う勇気を持つ
日本企業特有の“前例踏襲”思考は安心材料ですが、新規事業フェーズでは足かせになることも多いです。世間一般で良いとされている制度や働き方も、自社フェーズや人員構成によっては逆効果になることがあります。実際、「大企業流のOKR制度」を導入したものの、初期メンバーには負荷が高くモチベーション低下につながった経験もあります。「これ、本当に今ウチに合っている?」と自問自答し続けることをおすすめします。
まとめ:正解は一つじゃない
立ち上げ期には完璧な組織デザインなんて存在しません。大切なのは「小さく試して、うまくいかなければ即修正する」その柔軟さと誠実さです。そして何より、「人」が主役であることを忘れず、一人ひとりの声に耳を傾け続ける姿勢が成功への鍵だと痛感しています。
6. スムーズなチームビルディングのために
日本のビジネス文化を活かしたコミュニケーション
新規事業立ち上げ期において、コアメンバーを採用した後は、いかにして円滑なチームビルディングを行うかが大きな課題となります。日本のビジネス文化では、「ホウレンソウ」(報告・連絡・相談)が非常に重視されています。情報共有や状況報告をこまめに行い、メンバー同士が安心して意見交換できる雰囲気を作ることが大切です。また、上司やリーダーが率先してオープンなコミュニケーションを実践することで、組織全体に信頼感が広がります。
信頼関係構築の実践的な方法
日本企業では、直接的な指示よりも「阿吽の呼吸」や「空気を読む」といった暗黙の了解が多く存在します。しかし、新規事業の場合は多様なバックグラウンドを持つ人材が集まるため、なるべく明確な言葉で意図や期待値を伝えることが肝心です。そのうえで、雑談やランチミーティングなど非公式なコミュニケーションの場も積極的に設け、お互いの人柄や価値観を理解し合う努力をしましょう。信頼関係は短期間で築けるものではありませんが、小さな約束を守り合うことで徐々に深まっていきます。
組織まとめ役としての心得
リーダーやマネージャーには、「聞き役」に徹する姿勢も重要です。一方的に指示するだけでなく、現場の声や悩みに耳を傾けることで、メンバーからの信頼と共感を得ることができます。また、日本特有の「根回し」を活用し、大きな決断や方針転換の前にはキーパーソンと事前に意見交換しておくことも効果的です。この地道な調整力こそが、混乱を避けてスムーズに組織をまとめあげるコツです。
まとめ:誠実さと柔軟性を忘れずに
新規事業立ち上げ期は、不確実性やストレスも多いですが、日本らしい誠実さと丁寧なコミュニケーションを徹底することで、強固なチームワークと信頼関係が生まれます。どんな困難にも正直に向き合い、小さな成功体験を積み重ねながら、メンバー一人ひとりと真摯に向き合うことが、最終的には組織全体の成長につながります。


