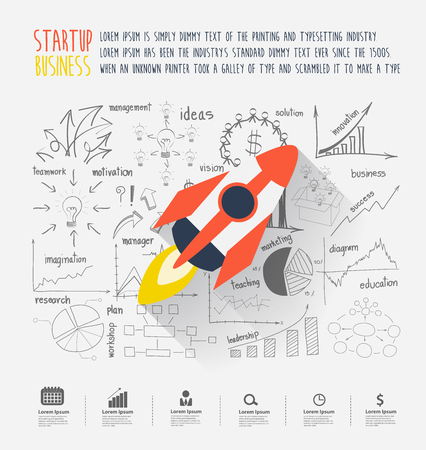1. メーカー勤務時代の経験と学び
私は日本の大手メーカーで長年働いてきました。メーカーという現場は、効率や品質を追求するだけでなく、チームワークやコミュニケーションが非常に重視される場所です。日々の業務を通じて、納期やコスト管理、製品開発の現場で培った論理的思考力や問題解決能力は、今でも私の財産となっています。また、多様な部署や立場の人たちと協力しながら目標を達成する中で、人間関係の大切さを強く実感しました。失敗した時には仲間と共に原因を追究し、成功した時には皆で喜び合う――そうした日々の積み重ねが、仕事への責任感や信頼関係を築く基礎となりました。メーカー勤務時代のこうした経験は、後に日本酒バー創業という新しい挑戦へと踏み出す際にも、大きな支えとなったのです。
2. 日本酒との出会いと魅力への目覚め
メーカー勤務時代、私は全国各地を出張で訪れる機会が多くありました。その中で、初めて本格的に日本酒を味わったのは、東北地方の小さな居酒屋でした。地元の方が誇りをもって勧めてくださった一杯は、それまで抱いていた「辛口」「淡白」という先入観を覆し、芳醇な香りと米本来の甘み、そしてその土地ならではの水や気候による違いを感じさせてくれました。
その体験がきっかけとなり、日本酒に対する関心が一気に高まりました。日本各地には数え切れないほどの酒蔵が存在し、それぞれの歴史や造り手の想い、気候風土の違いが個性的な味わいを生み出しています。この奥深さこそが日本酒最大の魅力だと感じるようになりました。
地域ごとの日本酒の特徴
| 地域 | 特徴 | 代表的な酒蔵・銘柄 |
|---|---|---|
| 東北(新潟・山形など) | すっきりとした淡麗辛口 | 久保田(新潟)、十四代(山形) |
| 関西(兵庫・京都など) | 旨味が強くコクのある味わい | 獺祭(山口)、月桂冠(京都) |
| 九州(福岡・佐賀など) | 柔らかくまろやかな甘み | 繁枡(福岡)、鍋島(佐賀) |
現地でしか味わえない感動体験
旅先で地元の食材と共にいただく日本酒は、その土地の空気や人々とのふれあいも相まって、特別な思い出となりました。これらの経験を通じて、「もっと多くの人に地域ごとの日本酒の魅力を伝えたい」と強く感じるようになりました。

3. 創業の決意と家族・地域への想い
安定したメーカー勤務という道を歩んでいた私ですが、心のどこかで「本当に自分がやりたいことは何だろう」という問いが常にありました。ものづくりの現場で培った経験や知識を活かしつつ、自分自身の手で新たな価値を生み出したい――そんな思いが次第に強くなっていきました。そして、日本酒という日本文化の象徴を通じて、人々と深く繋がる場所を創りたいと考えるようになりました。
創業を決意するにあたり、まず頭に浮かんだのは家族や地元への想いでした。メーカー勤務は安定しており、家族にも安心感を与えていました。しかし、自分の夢を追うことで家族に負担をかけるのではないか、地元の方々に受け入れてもらえるのだろうかという不安もありました。それでも、「挑戦しない後悔」よりも、「挑戦することで得られる成長」を信じたい気持ちが勝り、一歩踏み出す決断をしました。
私の故郷は、古くから酒造りが盛んな地域です。子どもの頃から親しんできた日本酒には、家族との思い出や地元ならではの温かな交流が詰まっています。この土地だからこそできる日本酒バーを開くことで、地元に恩返ししたいという気持ちもありました。また、家族も最初は戸惑いながらも、私の情熱と誠意に共感して背中を押してくれました。
メーカー勤務時代には見えなかった「人と人との繋がり」の大切さや、地域社会に根ざした事業の意義に気づけたことも、大きな転機となりました。これからは、日本酒バーを通じて多くの方々に喜びと感動を届け、家族や地元への感謝の気持ちを形にしていきたいと考えています。
4. 開業準備のリアル――物件選びから地域連携まで
メーカー勤務から日本酒バーを創業するという新たな挑戦において、開業準備は想像以上に多岐にわたりました。特に物件探しや酒蔵訪問、そして地域の方々との繋がりづくりは、事業の基盤となる大切なステップでした。
物件探し:理想と現実のバランス
まず最初に直面したのが、日本酒バーに最適な物件探しです。アクセスの良さ、広さ、家賃、そして雰囲気など、多くの条件を比較検討しました。
下記の表は、私が重視したポイントと実際に候補となった物件の比較です。
| ポイント | A物件(駅近) | B物件(住宅街) |
|---|---|---|
| 立地 | 駅から徒歩3分 | 駅から徒歩10分 |
| 家賃 | 高い | 手頃 |
| 広さ | 20坪 | 15坪 |
| 雰囲気 | モダン | 和風レトロ |
最終的には、「地域との繋がり」を重視してB物件を選びました。住宅街ならではの落ち着いた環境と、地元住民との距離の近さが魅力だったからです。
酒蔵訪問:本物の日本酒を知る旅
メーカー時代の人脈を活かし、全国各地の酒蔵を自ら訪問しました。現地で杜氏や蔵人と直接話し、製造工程へのこだわりや地域ごとの味わいの違いを体感することで、自分自身の「日本酒観」が大きく広がりました。仕入れ先として信頼できる蔵元を見極めるためにも、このフィールドワークは欠かせないものとなりました。
地域連携:まち全体でつくる日本酒バー
開業準備を進める中で特に意識したのは、単なる飲食店ではなく「地域資源」として愛される場づくりです。町内会や商店街の集まりに積極的に参加し、地元のお祭りやイベントにも顔を出すよう心がけました。また、ご近所のお米農家さんや八百屋さんとも連携し、地域食材を使ったおつまみメニューも開発しました。
地域連携による取り組み例
| 連携先 | 具体的な取り組み内容 |
|---|---|
| 地元農家さん | 旬野菜のおつまみ提供・季節限定メニュー開発 |
| 酒蔵・蔵元 | オリジナル銘柄販売・試飲会共催 |
| 町内会・商店街 | イベント協賛・地域清掃活動への参加 |
こうした一つ一つの積み重ねが、日本酒バー開業後も地域のお客様から応援いただける基盤につながっています。
5. こだわりの日本酒セレクションとお客様体験
日本各地の酒蔵との出会いと対話
メーカー勤務時代には見ることができなかった、日本全国の酒蔵を自ら訪ね歩く日々。現地に足を運び、蔵元や杜氏と直接コミュニケーションを重ねる中で、それぞれの土地が持つ風土や哲学、そして造り手の情熱に触れることができました。たとえば、秋田の寒冷な気候が生み出すキリッとした味わいの純米酒や、広島の軟水を活かした柔らかな口当たりの吟醸酒など、地域ごとの個性を大切にした銘柄選びにこだわりました。
「物語」を感じる一杯を
当店では、単なる飲み比べではなく、お客様が一杯ごとにその背景やストーリーを感じられる体験を提供したいと考えています。それぞれのお酒について、蔵元から直接聞いたエピソードや現地で見聞きした風景、仕込み水や米へのこだわりなど、詳しくご紹介します。お客様がグラスを傾けながら、「このお酒はどんな人たちが、どんな思いで造っているんだろう」と想像し、会話が弾むような場づくりを心掛けています。
地域連携による限定メニュー
また、各地の酒蔵とのネットワークを活かし、季節限定の銘柄や小規模生産の希少なお酒も積極的にラインナップしています。日本酒だけでなく、その土地ならではのおつまみや伝統料理とのペアリングもご提案。新たな発見や驚きがある「ここだけの味わい」を楽しんでいただけるよう努めています。
お客様一人ひとりに寄り添うサービス
初心者から愛好家まで幅広いお客様が安心して楽しめるよう、日本酒選びや飲み方について丁寧にサポートすることも大切にしています。「辛口」「甘口」など好みをヒアリングしながら、その方にぴったりの一杯をご案内。メーカー勤務時代に培った知識と現場で得た経験を活かし、日本酒バーならではの温かなおもてなしで、お客様の日常に小さな特別感をお届けしています。
6. 経営者としての挑戦とこれからの目標
日本酒バーを運営する中で、私は単なる飲食店経営者という立場にとどまらず、地域社会との連携や地元課題への貢献も大切な使命だと感じています。メーカー勤務時代には見えなかった現場のリアルな声や、地域に根ざした人々の想いに触れることで、より強くその必要性を認識しました。
地域課題への取り組み
私たちの日本酒バーは、地域の小規模酒蔵と積極的に連携し、地元産の日本酒の魅力発信に努めています。近年では人口減少や高齢化による地元経済の縮小が課題となっているため、地元農家や伝統産業ともコラボレーションイベントを開催し、地域資源を活用した新しい価値創造を目指しています。また、「地酒×郷土料理」のペアリング提案や、日本酒初心者向けのワークショップを通じて、地域住民だけでなく観光客にも日本文化を体験していただける場づくりにも力を入れています。
今後実現したいビジョン
今後は、日本酒バーという枠を超えて、地域全体の活性化に貢献するプラットフォームへと進化させたいと考えています。具体的には、
・地元酒蔵ツーリズムとの連携強化
・若手杜氏や後継者育成プロジェクト
・海外への情報発信やインバウンド対応強化
など、多角的な取り組みを展開していく予定です。メーカー勤務で培ったネットワークや知見も活かしながら、地方から全国へ、そして世界へと日本酒文化の魅力を発信し続けていきたいと思います。
まとめ
メーカー勤務から一転して経営者となった今、日々新たな挑戦に直面しながらも、その一つひとつが自分自身や地域社会の成長につながっていることを実感しています。これからも「日本酒バー」を核として、人・モノ・文化が出会う場所を育て、日本酒と地域の未来を共につくっていきたいと思います。